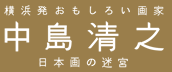大正・昭和の激動の時代。進取の気風あふれる街・横浜に生き、
型に嵌(はま)らない、しなやかな感性で、「日本画」に挑み続けた画家がいた――。
中島清之(なかじまきよし)という画家を知っていますか。その名を知る人々も、思い浮かぶ作品は、実に様々かもしれません。豊かな才気と旺盛な好奇心に満ち、常に新しい様式と手法に挑戦し続けた清之は、一見同じ画家とは思われないほど多彩な作品世界を展開し、「変転の画家」と評されました。
清之は、京都での少年期から培われた仏教美術への知識と共感、そして安雅堂画塾(あんがどうがじゅく)での古画研究で得た卓越した筆技を有しながら、清新な花鳥画から大胆にデフォルメされた人物画、幾何学的な抽象表現まで、周囲を驚かすほど様々な作風を示し、日本画の可能性を追求しました。自由奔放で、時にユーモアやアイロニーに満ちた多様な作品群は、中島清之という作家像を絞り込もうとする鑑賞者を惑わせ、まるで「迷宮」に誘い込むかのような魅力を備えています。
本展では、初公開作品、さらに画稿やスケッチを含む約180点を展観し、青年期から最晩年に至る清之の画業をたどり、主題や技法への関心のありようとその変遷を探ります。さらに下図やスケッチも紹介し、画面構成上の工夫を考察します。大正から戦前・戦後の昭和という、社会や価値観が大きく変容する時代の中で、一見激しい作風の変化を示しながら、清之が生涯にわたって貫いた思想や美意識はどういったものであったのか、編年的な構成により掘り下げていきます。
※会期中、一部作品の展示替えあり。
※作品をクリックすると、大きな画像でご覧いただけます。
第1章 青年期の研鑽-古典との出会い
小学校の頃から教師に頼まれて東大寺の紋様集などを模写していたという清之は、16歳で画家を目指して生まれ故郷の京都を離れ、叔父を頼りに横浜に出てきました。会社勤めをしながら、伝統的な古画の模写に励み、また「スケッチ魔」と言われるほど寸暇を惜しんで屋内外でのスケッチを行い、写実的な描写力を獲得していきました。25歳で院展に初入選し、下村観山(しもむらかんざん)や安田靫彦(やすだゆきひこ)、前田青邨(まえだせいそん)らの知遇を得ると、院展の本流である古典研究に根ざしつつ、次第に自らの感性を活かした装飾的な画面作りを展開していきます。やがて、垂直と水平の線、あるいは円と直線による幾何学的な構成への関心を示すようになり、《庫裏》や《花に寄る猫》といった大胆な構図の作品に結実させます。
 《横浜港風景》
《横浜港風景》
1920-30年頃(大正末期-昭和初期)、紙本着色・額、
おぶせミュージアム・中島千波館蔵 《胡瓜》
《胡瓜》
1923(大正12)年、絹本着色・額、
福島県立美術館蔵 《花に寄る猫》
《花に寄る猫》
1934(昭和9)年、紙本着色・額、
個人蔵(大佛次郎旧蔵)
第2章 戦中から戦後へ-色彩と構図の洗練
清之は1930(昭和5)年に31歳で妻・三代子と結婚します。翌年には長女が生まれ、生活は充実を増しますが、この年に満州事変が起き、さらに翌年には五・一五事件が勃発し、世の中は戦争への道を歩み始めていました。
1938(昭和13)年、陸軍慰問使として中国に赴いた清之は、兵士たちの似顔絵を描くかたわら、行く先々の街をスケッチしました。そして翌年再び中国を訪ね、当時の風俗を活写した《黄街(こうがい)》七部作を描きます。続いて、春日大社の祭礼を描いた《おん祭》七部作を発表し、これらの作品によって、気品ある色彩と洗練された構図の中に、ユーモアと情感を湛えた人物を描き出す表現に到達します。
1944(昭和19)年、清之は戦火を逃れ、家族とともに長野県の小布施村に疎開します。そして横浜に戻るまでの3年間、雪国の暮らしや山々に囲まれた風景を、数多く描き残しました。中央画壇から離れていることへの焦燥感に駆られながらも、「温かい人情に触れながら、美しく、かつ厳しい自然に包まれた信州での3年間は、その後の私の画風に、とても良い影響をもたらしたこともまた事実」と、清之は語っています。
終戦から2年を経て横浜に戻った清之は、社会や価値観の急速な変化に大きな戸惑いを感じていました。「世相の急旋回」への反発を感じながら、自分らしい主題を模索し、そして辿りついたのが、1950(昭和25)年の《方広会(ほごえ)の夜》でした。崇高さを感じさせるその画面は、戦後の混迷を脱して新しい時代の芸術を創出しようとする清之自身の、静かで厳しい覚悟を象徴するものでもありました。
 《おん祭 四、馬長稚児》
《おん祭 四、馬長稚児》
1942(昭和17)年、紙本着色・額、
おぶせミュージアム・中島千波館蔵 《雪の子(晴雪)》
《雪の子(晴雪)》
1946(昭和21)年、紙本着色・額、
横浜美術館蔵(中島清之氏寄贈) 《方広会の夜》
《方広会の夜》
1950(昭和25)年、紙本着色・二曲屏風一隻、
横浜美術館蔵(山口久像氏寄贈)
第3章 円熟期の画業-伝統と現代の統合への、たゆみなき挑戦
《方広会の夜》によって高い評価を得た清之は、同じ作品傾向にとどまることはなく、国内外の美術の最新動向を敏感に察知しながら、次々と新しい手法に挑戦していきました。1960(昭和35)年の《顔》は、アンフォルメル絵画に触発された鮮烈な赤の色調と重厚な絵肌によって、大画面に仏の顔だけを大きく捉えたものです。幼少期に天平文化の美に出会った清之にとって、仏教芸術は自身の原点とも言えるもので、仏像や古刹をテーマにした作品は、戦後も繰り返し描かれます。
また清之は同時期に、渓流や山肌などの自然の形象を、抽象的に捉えた作品に取り組むようになります。さらにモチーフは、伝統芸能から人気歌手、家族や友人の肖像、庭の花木、好んで旅をした瀬戸内海や富士山の風景など、実に多岐に渡りました。とりわけ、晩年に描いた人物像は、時に飄々としたユーモアやアイロニーに富み、清之生得の、鋭くも温かい人間観察力を伝えています。
清之の創造意欲は、80歳を目前にしても尚、衰えることはありませんでした。78歳で着手した三溪園臨春閣(さんけいえんりんしゅんかく)の襖絵では、若い頃から傾倒した琳派研究の成果を発揮し、写実と装飾性を両立させたダイナミックな画面を作り上げました。モチーフと構成は各室ごとに大きく変化に富み、五室五様に画家の渾身の力が漲(みなぎ)り、観る者を圧倒します。まさに70年間の画業の集大成と呼ぶにふさわしい作品です。
 《顔》
《顔》
1960(昭和35)年、紙本着色・額、
東京藝術大学美術館蔵 《川風》
《川風》
1964(昭和39)年、紙本着色・二曲屏風一隻、
東京国立近代美術館蔵 《鶴図 三渓園臨春閣襖絵》(部分)
《鶴図 三渓園臨春閣襖絵》(部分)
1977(昭和52)年、紙本着色・襖11面、
三溪園蔵、11/3~12/2展示 《若草》
《若草》
1978(昭和53)年、紙本着色・二曲屏風一隻、
佐野美術館蔵 《喝采》
《喝采》
1973(昭和48)年、紙本着色・額、
横浜美術館蔵(中島清之氏寄贈) 《霧氷》
《霧氷》
1963(昭和38)年、紙本着色・二曲屏風一隻、
横浜美術館蔵(中島清之氏寄贈)
中島 清之NAKAJIMA Kiyoshi
1899(明治32)年、現在の京都市山科区に生まれる。16歳で横浜に転居し、会社勤務をしながら松本楓湖(まつもとふうこ)の安雅堂画塾に通う。25歳で院展に初入選。以後4度の日本美術院賞を受賞し、同人となり、院展の中核として活躍。戦時中に小布施村(現・長野県上高井郡小布施町)に疎開した3年間以外は、横浜を拠点とし、横浜の美術界の発展と歩みを共にした。
最晩年には、三溪園(横浜市中区)の臨春閣の襖絵を手がけ、古典とモダニズムを統合させた清之芸術の集大成を示した。第五室までを完成させた1981(昭和56)年、病を得て、三男の中島千波に襖絵の制作を託す。静養生活ののち、1989(平成元)年に没した。
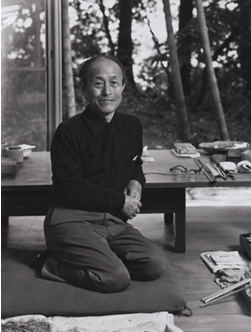 アトリエにて 1970(昭和45)年 71歳頃
アトリエにて 1970(昭和45)年 71歳頃