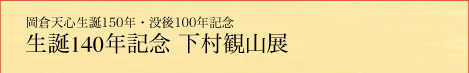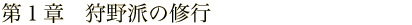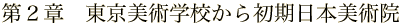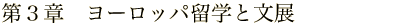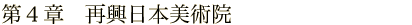下村観山(本名:晴三郎)の絵画修業は、明治15年、9歳の頃に始まりました。 前年に一家で和歌山から東京に移住した観山は、祖父の友人の

≪
紙本着色、軸 59.0×38.5cm
横浜美術館蔵
通期展示

≪鷹之図≫ 明治19年(1886)
紙本墨画、軸 66.0×50.0㎝
永青文庫蔵
展示期間:後期
明治22年、東京美術学校(以下「美校」)が開校すると、観山は、横山大観らとともに第1期生として入学し、翌年2代目校長として着任した岡倉天心の薫陶を受けることとなりました。「観山」の画号は、美校入学の頃に使い始めたとされています。美校では、再び狩野派の筆法の修練から始めることとなりましたが、すでに

≪辻説法≫ 明治25年(1892) 紙本着色、額 44.7×62.8㎝
横浜美術館蔵
展示期間:2013/12/7-2014/1/14

≪仏誕≫ 明治29年(1896)
絹本着色、軸 203.0×143.5㎝
東京藝術大学蔵
展示期間:2014/1/15-2/11

≪熊野観花≫ 明治27年(1894) 絹本着色、額 61.3×119.7㎝
東京藝術大学蔵
展示期間:2014/1/15-2/11
明治31年、美校内部の確執に端を発し、天心は校長の職を追われることとなりました。観山は天心に殉じて、大観や春草ら他の教職員とともに美校を去り、天心や、同志とともに、「日本美術院」を設立しました。観山は、日本美術院が日本絵画協会との連合展として開催した第1回日本美術院展に、釈迦が

≪闍維≫ 明治31年(1898) 絹本着色、額 143.7×256.0㎝ 横浜美術館蔵
通期展示

≪元禄美人図(三味線図)≫ 明治32年(1899)
紙本着色、二曲屏風一双の右隻
154.3×174.4㎝ 石水博物館蔵
通期展示


春日野は、現在の奈良公園一帯の台地の名称。その中にある春日大社の境内は
≪春日野≫ 明治33年(1900)
絹本着色、軸 162.0×114.0㎝
横浜美術館蔵
展示期間:2013/12/7-2014/1/14
明治34年、観山は美校に教授として復帰しました。その2年後、文部省の命により英国に渡り、色彩の研究を第一の目的として、西洋画の研究や模写を行いました。大英博物館にある模写を写したとされる《椅子の聖母》や、英国留学のあと欧州を巡遊した際にウフィーツィ美術館で写したものと思われる《まひわの聖母》といったラファエロの模写は、板に油彩で描かれた原画の柔らかな明暗を、水彩によって見事に絹に写し、観山の技術の確かさを示しています。
一方、日本美術院の活動は次第に停滞し、明治36年をもって経済的に立ちゆかなくなり、観山の帰国翌年の明治39年には、天心の別荘のあった茨城県の

≪ラファエロ作「椅子の聖母」(模写)≫
明治37年(1904) 絹本着色、額 56.0×54.5㎝
横浜美術館蔵
通期展示


≪木の間の秋≫ 明治40年(1907) 紙本着色、二曲屏風一双
各169.5×170.0㎝
東京国立近代美術館蔵
展示期間:後期



≪小倉山≫ 明治42年(1909) 絹本着色、六曲屏風一双 各157.0×333.5㎝ 横浜美術館蔵 通期展示
平安時代中期の公卿・政治家であった藤原忠平が、『百人一首』に撰せられた和歌「をぐら山峰のもみぢ葉心あらば今ひとたびのみゆき待たなむ」(小倉山の紅葉よ、もし心があるならば、今一度行幸があるまで散らずに待っていてほしい)の歌想を得る様が描かれる。「堀塗り」「付け立て」「垂らしこみ」といったやまと絵の技巧が駆使され、琳派風の鮮やかな意匠性が目を引く。
大正2年の末、観山は天心を通じて知遇を得た実業家・原三溪の招きにより、横浜本牧の和田山に新邸を設け、家族とともに移りました。以降、三溪の支援のもとで制作をするようになり、二人の交流は観山が亡くなるまで続きました。この年、ボストン美術館の収集活動を託されていた天心が、健康状態の悪化により帰国し、療養中の赤倉の山荘で亡くなりました。天心の臨終に際し、観山と大観は、有名無実化していた日本美術院の再興をはかります。観山は文展審査員を辞して、在野を貫く決意を示しました。再興日本美術院の創立同人には、他に木村武山、


≪白狐≫ 大正3年(1914) 紙本着色、二曲屏風一双 各186.8×208.4㎝
東京国立博物館蔵 TNM Image Archives
展示期間:2013/12/7-12/20



≪弱法師≫ 大正4年(1915) 絹本金地着色、六曲屏風一双 各187.5×407.0㎝ 東京国立博物館蔵 TNM Image Archives
展示期間:2013/12/7-12/20
謡曲『弱法師』を主題にする。偽りの告げ口により父

≪酔李白≫ 大正7年(1918)
絹本着色、軸 151.0×69.0㎝
北野美術館蔵
通期展示
![]()

![]()
≪魚籃観音≫ 昭和3年(1928)
絹本着色、軸(三幅対)
中幅158.0×55.7 左右各158.5×32.3㎝
西中山 妙福寺蔵
通期展示
魚籃観音は、観音菩薩が三十三の姿に


≪松二鶴≫ 昭和2年(1927) 絹本着色、六曲屏風一双 各177.5×375.0㎝ 横浜美術館蔵
展示期間:2013/12/21-2014/2/11
老いた赤松の大木のもとに、真鶴二羽とその幼鳥三羽が憩う様が描かれている。齢千年に達するという鶴は、様々な伝説や故事を持つ松の古木に配されて古くから描かれ、「